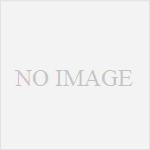ダイエット検定1級 栄養素とカロリー計算
ダイエット検定1級のテキストから、今回も学習内容をシェアしていきます。
検定受験に限らず、ダイエットの専門的な知識習得にお役立て下さい。
2016年3月18日、今日は初夏のような暖かい一日になりましたね。
名古屋では、後数日で桜の開花だそうで。
おかげで花粉症の症状も一気に進み、暫くは憂鬱な日々が続きそうです。
鼻の穴入り口辺りにワセリンを塗ると、花粉症の症状を抑えるのに
効果があるとヤフーニュースで見ました・・・実際どうなんでしょうかね?
では本題、ダイエット検定1級の学習に行きましょう。
3回目のテーマは、第1章「ダイエットと栄養素 応用編」から設問3、
3大栄養素の具体的なカロリー計算方法について学んでいきます。
計算式は非常にシンプルで、
各栄養素の1g当たりのカロリーというのが決まっているので、
その食材にその栄養素が何グラム含まれてるか分かれば、
1g辺りのカロリーに重量を掛けることで求めることができます。
例題1.食パンにバターを5g塗ると、追加されるカロリーはどれぐらいになるか?
バターの成分は殆どが油脂であり、
脂質は1g当たり9kcalなので、5g x 9kcal = 45kcal
例題2.砂糖を大さじ1杯分(約9g)コーヒーに入れると、カロリーはどれぐらい増えるか?
砂糖はそのまま糖質(炭水化物) と捉え、1g当たり4kcalなので、
9g x 4kcal = 36kcal 増えることになります。
尚、コーヒー自体のカロリーは0kcalなのだそうです。
また、例題には出てきませんでしたが、
3大栄養素の残りの1つである たんぱく質では1gあたりのカロリーは4kcalです。
以上のように、3大栄養素(たんぱく質、脂質、糖質)のそれぞれの含有重量が分かれば
その食品の総カロリーを簡単に求めることができます。
以前2級のテキストでは、
”ダイエット時のメニューや食材選びでは”総カロリーを見るのではなく、
そのカロリーが何の栄養素を示しているのかが重要であることを学んでいました。
今回の計算方法と併せて、改めて覚えておきましょう。
<参考書籍:ダイエット検定1級テキスト(日本ダイエット健康協会)>